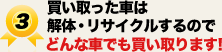横浜国立大学フォーミュラプロジェクトにて2016年のチームリーダーを務めました植松と申します。今回は、自動車(特にレーシングカー)と空気力学の関係について基礎的な内容を述べます。まだまだ浅学な筆者の為、以下述べる内容には至らない点や間違いなどが見受けられるかもしれませんが、その点は予めご了承下さい。
さて、レーシングカーの性能を評価する際、大きく分けて、エンジン・シャシー(足回り)・空力などが、あります。とくに近年は、空力の要素が非常に大きくなっています。例えばF1においては、最高時速は300km/hを超え、旋回時は5~6G相当の横方向の力を受けるほど高速です。ちなみに、サーキット内における歴代最高速度は約370km/hです。これらを可能にしているのは、車体周りの空気力の作用です。そして空気の流れ(運動)や物体が空気から受ける作用を取り扱う学問を「空気力学(Aerodynamics)」と言います。
空気力学は、広く言うと「流体力学」の一部分ですが、では空気と液体などの他の流体の違いは何でしょうか?それは、空気というのは「圧縮性を持つ = 流体の密度が変化する」事です。皆さんは注射器のようなピストンに、空気や水を入れて動かしたことはあるでしょうか。空気を入れた場合は力を加えると圧縮させる事が可能ですが、水を入れた場合にはどんなに力を入れても人間の力では圧縮する事が出来ません。
空気の圧縮性を考慮する必要な速度域は、100m/s、或いは約300km/h以上です。地上を走る乗用車の速度域では、周囲の流体は非圧縮性であると考えても良いでしょうが、レーシングカーの場合、厳密に解析を行うにはやはり圧縮性の考慮が必要になります。この圧縮性の議論を起点に、流体力学から派生した空気力学は、航空機・宇宙機の発展と共に大きく発展し体系化されてきました。そしてF1を始めとするレーシングカーの空力開発においては、既存の空力の理論に加え、風洞実験やCFD(後述)による流れのシミュレーションを駆使しながら性能の向上に役立てています。
車がサーキットを速く走る為に必要な事は、端的に述べると、タイヤに対してより大きな荷重を与える事です。タイヤに荷重が加わる事により、加減速・旋回において高い性能を発揮する事が可能となるからです。
ではタイヤに荷重を加える為に、より車体の重量を重くすれば良いのでしょうか。お分かりだと思いますがそうではありません。実際には重量を増加させるほど、より大きなタイヤのグリップが必要になります。
例えば、車重を増加させる事によりタイヤに与える荷重を2倍にさせた際、旋回中のコーナリングフォースが2倍に増えるのかというとそんな事は有り得ず、同じ速度で旋回するには2倍のグリップ力が必要になります。ですから、車両はより軽量にしてなるべく慣性を減少させるように設計されていきます。よって、車重を抑えながらもタイヤに対して大きな荷重を加える必要があります。
そこで“ダウンフォース”という空気力の活用を考えます。ダウンフォースとは、車体周りの気流が生み出す圧力差により車体を地面方向に押し付ける力の事です。より厳密には、空気力の合力ベクトルのうち下方向の成分を抜き出したものです。これを利用する事によって、車重をそれほど増加させる事無くタイヤに荷重を与える事が可能になるという訳です。
ダウンフォースを得る為の空力パーツとしては、スプリッターやスポイラー、エアダムなどもありますが、もっとも一般的なのはやはり翼(Wing)でしょう。簡単に翼の原理を示します。次に示すのは翼の2次元断面です。
図に示したうち、翼弦長・翼厚・キャンバー・迎角などが翼のパラメータです。既にこれらのパラメータを様々に変化させながらその特性が調べられており、それぞれにおける断面形状を「翼型」と呼びます。通常は、数ある翼型の中から適したものを選定して使用する事が多いです。
この翼周りを左から右へ向けて流れる空気により、どのような作用が生じるかを見ていきます。次に示すのは、ある翼断面周りの流れの例です。迎角は4°である為、図中に矢印で示した通り水平よりも4°上方から流れが来ています。
まず翼の上面、特に前縁近くが高圧になります。また、下面の特に前縁近くでは流速が大きく高められる事で負圧が生じ、翼は下方向の力つまりダウンフォースを受ける事になります。
また、これはあくまで翼の断面のみを表しており、3次元で見ると必ず翼端を考慮しなければなりません。翼端では高圧の上面から低圧な下面に向けて空気が流れます。これが連続的に起こる事で、翼端から後流に向けて翼端渦と呼ばれるものが定在する事になります。この時、上面から下面への空気の漏れにより圧力差は小さくなり、ダウンフォースが低下してしまいます。
航空機の場合にはスパン長(翼断面方向から見た時の奥行)を大きく取る事で翼端の影響を小さくする事が出来ますが、車の場合には車幅以上の大きな翼を用いる事は現実的であるとは言えません。実際1960年代後半のF1ではスパン長をどんどん大きくしていった結果重大な事故に繋がった事から、スパン長の上限が定められ規制される事になりました。そこで翼端からの空気の漏れを防ぐ為に、次に示すような翼端版(エンドプレート)が導入されます。
翼端版により上面の高圧な空気は上面に留まり、下面では低圧が保たれます。また、渦の発生自体が抗力(進行方向と逆向き成分の空気力)の増加に繋がりますが、翼端版は渦の発生もある程度抑える事が出来る為、抗力増加の抑制にも繋がります。
ここで抗力の話が出てきましたので、一度この力に関しても触れておきます。抗力は大きく分けて4つに分類されます。普通乗用車が100km/hで走行する際の全抵抗に対する内訳とともに示します。
①摩擦抵抗:空気の持つ粘性により物体に作用する摩擦力(約8%)
②形状抵抗:流れが剥離した時の圧力差により生じる抵抗(約67%)
③誘導抵抗:縦渦発生によるエネルギー損失に対応する抵抗(約8%)
④干渉抵抗:複数の物体が互いの流れに干渉する事で生じる抗力(約17%)
以上より、普通乗用車においては形状抵抗が大半を占め、流れが剥離しないような流線型の形状を用いる事で抗力を小さく抑える事が出来ると言えます。
翼単体についても剥離を抑え抗力を抑える工夫があります。それは、大きなウィングの代わりに小さなウィングを並べて配置する事です。
上の図に示すように、小型の二枚の翼を用いる事により、後縁での流れの剥離が抑えられ、尚且つより大きなダウンフォースを得られる事が分かります。現在のF1は、5枚以上ものエレメントからなるフロントウィングを使用しています。
ここでは空力開発に必須の実験設備である風洞について紹介します。風洞とは、実車又は模型を計測室”洞”に設置し、そこに大型の送風機を用いて空気”風”を流す事で車両周りの流れを模擬的に作り出し、空気力の測定や流れの可視化などを行う設備です。
実際に走行する車は、静止した空気中を通過していきますが、逆に静止した車に空気が流れていると考える事も出来ます。しかし、実際の流れを完全に模擬出来るのかというと、幾つか異なる点があります。最も大きな違いは、路面(床表面)の流れです。
上に書いたように、実際の車両は静止した路面を移動していく訳ですから、路面と車の間には相対速度があります。しかし、風洞の場合は、車両が静止しており、路面も静止しています。本来は後方へ動いてゆくはずの路面が静止している為、路面付近の流れが大きく異なってしまうのです。この原因には、流体の持つ性質の一つである境界層の生成があります。
空気を含む恐らくほぼ全ての流体は粘性を持つ為、物体の表面に付着し、そこから幾らかの厚みの範囲では速度の遅い領域つまり境界層が形成されます。同様に、風洞の動かない床面にも速度をほとんど持たない層が存在し、完全な流れの再現を妨げています。
そしてこの影響を小さくする為に、境界層吸い込み装置やムービング・ベルトなどの装置が考案されています。ムービング・ベルトは文字通りベルト状の床面が流速と同じ速度で移動します。これにより比較的実際の流れを忠実に再現出来ますが、設備は大掛かりなものになります。
空気力の測定には、主に6分力天秤が用いられます。6分力とは、3つの軸方向に対応する抗力・横力・揚力の3つと、各軸回りの3つのモーメントを表します。天秤の支持方法には大きく分けて、上部から支柱を固定するストラット方式、車両の後方から支持するスティング方式、各タイヤを直接天秤に設置する床置き式天秤などがあります。
次にコンピュータを用いて数値的に流れを解析する、CFD(数値流体力学)について述べます。CFDの優れた点は、得られる情報量が多い事です。例えば、物体表面の圧力分布・表面流線・速度分布などに加え、物体周りの空間の圧力分布・流線・渦度分布など、より詳細な流れ場を模擬する事が可能です。
ではCFDを用いれば万事が上手くいくのかというと、現在は未だその段階にはありません。CFDを正しく使用するには、流体力学や数値流体力学の知識が必要であり、また風洞実験の結果と照合する事により、計算で得られた結果が妥当であるのか、そうでなければどこに原因があるのかを突き止める必要があります。
簡単にCFDの使用手順を説明します。まずCADソフトなどを用いて、モデルの3Dデータを準備します。モデルの表面は隙間なく全て閉じた形状となっている必要があります。
次に解析空間のメッシュ(格子)生成を行います。メッシュ生成により、元々は連続的な物理量が、離散化された情報として各格子に入る事になります。現在は四面体による非構造格子が主流になっています。
次にこのデータをソルバに取り込み解析を行います。流速などの計算条件・境界条件・使用する乱流モデルなどの設定を行い、計算を開始します。計算終了後の処理はポストプロセスと呼ばれ、可視化用にデータを整理します。
F1では、60年代の終わりからダウンフォースを発生させる翼が、ようやく用いられるようになります。その後、70年代から80年代前半にかけて、F1以外の他のカテゴリーでもウィングカーと呼ばれる車体下面を翼形状にする車両が多く作られましたが、度重なる危険な事故により、車体の下面を平らに(フラットボトム化)する規則が設けられるようになります。その後90年代の途中から、ハイノーズを採用し前方から来る空気の流れを車体の下面に取り込む手法が確立されていきます。これは今に続く設計コンセプトであると思われます(2019年現在)。
以上、簡単にではありますが空気力学の基礎的な観点から自動車について述べてきました。最後までお読み頂きありがとうございました。
執筆:横浜国立大学フォーミュラプロジェクト:植松亮裕